

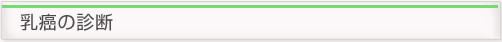
乳癌の症状は、腫瘤触知が最も多く、乳癌の80-90%が腫瘤で発見されます。
また、乳房の変形や血性乳頭分泌(乳首から出血)なども重要な症状ですので、下着が血液などで汚れていないかも気をつけてください。
その他、左右の大きさ、輪郭や形の変化、皮膚のくぼみ(えくぼ)やひきつれ、乳頭の陥没やただれ、分泌物の異常などをチェックしてください。
痛みは、乳癌では少ないのですが、大きな乳癌や周囲へ浸潤している場合には、痛むこともあります。
早期癌に相当する非浸潤癌の場合、腫瘤を形成しない非腫瘤性乳癌で、触知不能のケースも多く、マンモグラフィーによる微小石灰化のみが手がかりということもあります。
触診、マンモグラフィー、超音波エコーの3つの検査でほとんどの乳癌の診断が可能です。
近年、マンモグラフィー検診の普及により微小石灰化のみを兆候とする非触知乳癌が増加していますが、
その多くは非浸潤癌です。
微小石灰化がみられない非浸潤癌も多くなってきており、
その画像診断にはMRI、high resolution CTや超音波エラストグラフィー、さらには造影マンモグラフィーなどが有用です。
乳房温存手術には、取り残しを防ぐために、 乳癌の進展(広がり)の程度や多発病変の診断が重要です。実際の手術で切除範囲を決定するために、 dynamic CTやhigh resolution CTやMRIが用いられ、 最近ではPET/CTの利用も多くなっています。
乳癌の最終診断は病理診断です。
通常は、採血などに使用する細い針をつけた注射器を用いて腫瘍を穿刺し、
細胞を吸引して調べる穿刺吸引細胞診や、それよりも太い針を用いて腫瘍組織の一部を取り出す太針生検を行ないます。
これらに加えて、近年マンモトームとよばれる吸引組織生検が導入されています。これらの検査は腫瘍の一部を採取するだけですので、
癌細胞が検出されなくても100%安心という訳ではありません。
細胞診で癌細胞が検出されなくても、画像上、癌が疑わしい場合には、腫瘍を摘出して検査を行う切除生検が必要になります。
一般に、穿刺吸引細胞診は腫瘤を触知する場合は有用であるが、
非浸潤癌と浸潤癌の鑑別ができない欠点があります。
非触知の微小石灰化病変には、太針生検とマンモトームが有用であるが、
穿刺針が癌組織にうまく命中しているかが問題となります。いずれの検査も術者の熟練度が検査の決め手といえます。
また、乳頭から分泌物、特に血液の混じっている分泌物がある場合は、分泌物をガラス板にこすりつけて、 その中に癌細胞が混じっていないかを調べる塗沫細胞診を行ないます。
また、乳頭分泌物中の腫瘍マーカー(CEA)を調べるマンモテックという検査も有用です。
転移の診断にはCT、MRI、骨シンチグラフィー、PET/CTなどが用いられます。
CTはレントゲンを用いて人体を輪切り状に撮影する検査で、MRIは磁気を利用していろいろな角度から輪切り状に撮影する検査です。
骨シンチグラフィーは骨の転移巣に集まる放射性物質を注射してその放射性物質の骨への集まり具合を調べる検査です。
最近はこれらに加えてPET/CTが普及してきました。
PET/CTは癌細胞の栄養物質であるブドウ糖によく似た放射性物質を注射して、
その放射性物質の集まる場所を検査する方法です。
これらの検査は発見する転移巣の場所により得意、不得意がありますので、 いくつかの検査を組み合わせて調べます。
乳癌の診断を受けた場合、頭が混乱して「すぐに手術を受けなければ」とあせってしまいますが、
第一に大切なことは乳癌の進行度(臨床病期またはstageといいます)を診断することです。
病期によって、治療法が異なってくるからです。乳癌の臨床病期は、原発巣の大きさ、リンパ節転移の有無とその程度、
他の臓器への転移(遠隔転移)の有無、を組み合わせて、0期からIV期に分類されます。
最終的な臨床病期は手術後に切除した標本を顕微鏡で調べた病理検査によって行ないますが、 手術前は画像検査や細胞診、組織診の結果に基づいて行ないます。
次いで、治療法ですが、乳房温存を行う条件は医師によって方針が大きく異なりますので、 乳房切除をすすめられた場合はセカンドオピニオンを受けるとよいでしょう。 また、温存療法のガイドラインからはずれていても乳房温存手術が可能な場合も多いので、 一度ご相談ください。





















