

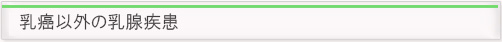
概略
乳管内乳頭腫 (IDP) は、乳腺小葉で産生分泌された乳汁が乳頭まで流れる「乳管」の中にできる良性の腫瘍で、35歳~55歳くらいの女性に多いとされています。IDP自体は良性ですが、10年ぐらいの間に1割ぐらいの割合で乳癌が発症するとされています。当院ではIDPの疑いで切除すると2割程度に乳癌(非浸潤性乳管癌や乳管内乳頭癌)が見られます。IDPが乳癌に進行するのか、IDPの近くに乳癌が併発するのかは現在のところ解明されていません。
IDPが乳管に沿って数珠つなぎに多発性に発症する乳頭腫症では、切除すると一部に非浸潤性乳管癌や異型乳管過形成が存在する事も多く、将来の乳癌発症の可能性もあります。以上の様に、IDPまたはIDPの疑いと診断された場合は、定期検査が必要です。当院の経験では、腫瘍の増大、微小石灰化の出現、出血の悪化は乳癌発症の兆候です。
症状
乳頭異常分泌、特に褐色や血液の混じった分泌が主症状で、乳頭近くに腫瘤を触れる場合もあります。また、乳頭から離れたところに発生することもあります。通常、痛みはありませんが、血性分泌の場合は痛む事があります。分泌物は、赤や茶褐色の血性が多いが、透明の場合もあります。液状のものが多いのですが、ゼリー状のものもあります。しぼらないとわからないものから、パッドが必要なほど多量にでるものまでいろいろです。
乳管内乳頭腫の診断
IDPを診断するよりは、IDPと乳癌の鑑別目的の検査になります。マンモグラフィーと超音波エコ−検査を行います。拡張乳管とその中に存在する腫瘤性病変として描出されますが、病変が小さい場合は画像検査で描出されないことがあります。また、非浸潤性乳管癌との鑑別が困難で、切除して初めて良悪性の診断が可能になる事も少なくありません。
分泌物の検査としては、第1に分泌物の細胞診を行ないます。腫瘤や石灰化を認めれば、その部位の穿刺細胞診を行います。細胞診では良悪性の診断しか出来ない事も多く、IDPと診断するのは困難です。第2に潜血反応を行います。当院のデータでは血液反応が3+の強陽性であれば、IDPか乳癌の可能性が高くなります。第3に分泌物中CEA測定を行います。CEAは癌細胞が産生する腫瘍マーカーで、分泌物が微量なため、免疫泳動法によるマンモテックという検査を行います。分泌物中CEAが400ng/mlまでが正常範囲で、当院のデータでは400 - 1000の場合はIDPが5割程度、乳癌が2−3割程度の頻度です。また1000以上の場合は90%以上の確率で乳癌です。
以前は、乳管造影という検査を行っていました。出血の見られる乳頭の乳管に細いプラスチックチューブを挿入し、そこから造影剤を注入して検査する方法です。乳管拡張が軽度の場合は挿入と造影が難しく、かなり苦痛を伴います。乳管内視鏡という検査もありますが、内視鏡が入る程に拡張した乳管の症例がそれほど多くなく、かなりの苦痛を伴います。最近では超音波エコーの性能が向上したため、乳管造影をしなくてもエコー検査だけで病変を描出できます。また、高解像度CTやMRIなどで鮮明に描出されるため、苦痛を伴う検査を行なう必要はありません。ただ、画像検査や細胞診を行っても鑑別できない場合もあり、切除標本の病理診断でも良悪性の診断が困難で、特殊な免疫染色により診断できる場合も少なくありません。
治療
以上のような検査で悪性の可能性が否定できない場合、診断と治療を兼ねて切除生検を行います。IDPの手術は、腺葉区域切除が標準となります。IDPの存在する拡張乳管を乳頭直下から乳管拡張の広がっている範囲までを切除します。通常は1本の乳管が多いのですが、2本の場合もあります。以前は乳管に色素を注入して色素の染まる範囲を切除していましたが、色素で染まる範囲よりも乳管拡張が広がっている事も多く、当院では、CTやMRIの画像を参考に、術中超音波エコ−検査を行いながら切除範囲を決定します。範囲が狭い場合は局所麻酔のみで手術が可能ですが、広い範囲の場合は全身麻酔が必要な場合もあります。
(または、放射状硬化性病変 Radial sclerosing lesion)
Radial scar (RS) は臨床的な意義が明確ではない良性増殖性の乳腺病変で、中心部の瘢痕様線維弾性組織とそれを放射状に取り巻く乳管や小葉より構成され、上皮過形成、硬化性腺症、囊疱状拡張等の病変が混在する複合病変です。
最近では、これらの病理組織像をより反映しているRadial sclerosing lesion (RSL) と呼ぶ病理医も多い様です。
RS は、近年の乳癌検診の普及に伴い、発見機会が増加しています。しかし、その画像所見が、乳癌、特に硬癌に類似する点が、臨床上の問題点です。また、しばしば、乳癌、特に非浸潤性乳管癌を合併する事があり、その頻度は、報告によりかなり差がありますが、0 – 25%と報告されています。また、異型性増殖病変(異型乳管上皮過形成)を伴うことがあり、術後の残存病変から癌が発生する可能性もあります。当院でも、乳癌を疑い乳房部分切除を行なったところ、病理学的にRSと診断された症例で、術後5年以上経過してから、残存乳房に非浸潤癌を発症した症例があります。
このため、術前の組織生検でRSと診断された場合でも、術式と切除範囲の設定は難しく、また、術後病理診断が良性のRSと診断されても、術後の定期検査は欠かせません。
FAは10~30代の若い女性の乳房にできる良性腫瘍で、若い女性の乳房腫瘤の8割以上がFAです。FAは炎症に近い腫瘍とされています。原因は不明ですが、思春期に乳腺の組織である線維組織や腺管が増え過ぎて、発症すると考えられています。病状の進行は個人差が大きく、一生、小さいままの人もいれば、時に5㎝を超える大きさになるケースもあります。また、1個だけでなく、数個もある場合や、両側の乳房にできる場合もあります。通常2-3cmになると増殖が止まり、60-70%は40才までに自然退縮するとされています。自然退縮しなかったFAの5%程度が増大するとされています。
FAは、硬さやマンモグラフィーや超音波エコーなどの所見が一部の乳癌に似ているため、癌との鑑別診断が大切です。診断は、通常、腫瘤を注射針で穿刺し、細胞を吸引して顕微鏡で調べる穿刺吸引細胞診やcore needle biopsy(太針生検)を行います。癌との鑑別が難しいケースでは、摘出して調べる切除生検を行うこともあります。
FAが小さい場合は経過を見るだけでよく、経過観察中に消えるケースもあります。しかし、2.5~3.0cmを超える場合は、急に大きくなったりすることがあります。急に大きくなった場合や乳房が変形するほど大きい場合は、摘出術が必要になります。また、FAそのものは癌化しませんが、まれに、内部に非浸潤癌や浸潤癌、また異型乳管過形成(ADH)等の前癌病変を伴うことがあります。30代後半以後のFAは癌の合併頻度が多くなるため、40才以降で急に大きくなるケースや微小石灰化が出現した場合には、摘出して癌がないかを調べることが必要です。
このようにFAは自然退縮がよくあるため、穿刺吸引細胞診で良性と診断された3cm以下のFAは、40歳未満であれば、原則として経過観察でよいとされています。手術の適応としては、3cmを越えて増大するもの、悪性腫瘍合併の疑い、葉状腫瘍との鑑別が困難なもの等が挙げられます。
手術は日帰りでできます。通常は1時間程度で、当院では手術跡が目立たないように吸収性の縫合糸を用いた埋没縫合という方法で手術を行っています。
経過観察は、約3 - 6ヶ月毎の定期検診で充分ですが、急に大きくなる場合や痛みが強くなった場合にはすぐに受診して下さい。
乳腺の葉状腫瘍 (Pyllodes tumor, PT) は、以前は悪性と考えられていたためにcystsarcoma pyllodes (葉状嚢胞肉腫)という名前がついていましたが、悪性型は10%程度であることがわかったため、葉状腫瘍と名前が変更されました。比較的柔らかい腫瘍で、30~50代の女性に多くみられます。急に大きくなることが特徴で、時に10cmを超える大きさになることもあり、潰瘍を作って噴火山のようになることもあります。
葉状腫瘍は、病理学的に良性(約70%)、境界型(約20%)、悪性(約10%)に分類されます。悪性のものは乳房にできた肉腫というべきもので、転移再発して死亡することもあります(全体の約5%とされています)。ただ、悪性と診断されても良性の経過をとるものや、良性と診断されても転移するものがあり、良・悪性の診断は必ずしも容易ではありません。また、骨軟骨化生を伴うもの(石灰化がみられることが多い)や、脂肪組織への浸潤のある場合は悪性度が高く、転移再発することが多いとされています。
治療は、手術が基本です。通常は摘出術を行いますが、非常に大きな場合や皮膚潰瘍を伴う場合は、乳房を切除することもあります。腋窩リンパ節への転移は、通常みられないため、腋窩リンパ節は切除しません。ただ、悪性の場合は転移することもあるため、CTやPET/CTなどを行ってリンパ節や肺などへの転移の有無を検査してから、リンパ節を切除するかどうかを決定します。葉状腫瘍の20~40%はホルモン受容体陽性であるが内分泌療法には反応しないため,内分泌療法は無効とされ、ガイドラインではその使用は推奨されないとされています。抗癌剤治療も効果は限定的とされていますが、ガイドラインではドキソルビシンやイホスファミドなどの軟部肉腫に対して用いる薬剤の使用が勧められています。悪性の場合、摘出後に放射線療法を行うこともあり、当院でも数例に行い、今のところ再発した症例はありませんが、効果は不明です。他院で切除手術を受け再発し、当院で再切除を行った再発悪性葉状腫瘍に対し術後放射線療法を行った2症例は、いずれも3年以上経過していますが、今のところ再再発は見られておりません。
手術は日帰りでできます。通常は1時間程度で、当院では手術跡が目立たないように吸収性の縫合糸を用いた埋没縫合という方法で手術を行っています。 経過観察は、当院では、良性の場合は約6ヶ月毎の定期検診を行いますが、手術を行った悪性や境界型の場合は3か月毎に診察を行ないます。
乳管腺腫は、乳頭状や樹枝状の構造を示さない乳管内の充実性良性腫瘍で、管状の腺管増殖と線維成分の増生から形成されます。以前は硬化性管内乳頭腫 (sclerotic intraductal papilloma)とされ、乳管内乳頭腫の一つの表現型とされてきました。
好発年齢は40-50歳前後で、80-90%以上が40歳以上とされます。
臨床所見としては腫瘤形成が多く、2cmを越えることは稀で、単発性と多発性の場合があります。
病理学的には、乳管内の腺管の増殖と線維成分の増生、強い硬化性変化がみられ、中心部に瘢痕様の線維化がみられます。上皮とともに間質成分が乳管壁を超えて増生する偽浸潤、アポクリン化生、微小石灰化がみられることもあります。
臨床的には、画像検査で癌と診断されることが多く、癌との鑑別が非常に難しいことが問題です。
マンモグラフィーでは、微細石灰化像を伴う腫瘤陰影を呈し、癌と誤診されることがあり、超音波エコ−では、不整形の充実性腫瘤像や囊胞内腫瘤像を呈することもあり、超音波エコーでの偽陽性率は60%ともいわれます。
造影MRIでも急峻な造影効果を示し、癌と診断された報告も多くあります。
このように、画像診断では良悪性の鑑別困難なことが多いのが難しい点です。
穿刺細胞診や太針生検での診断も難しく、乳管腺腫を疑った場合には確定診断を得るためには摘出生検をするべきとされています。
術中迅速病理診断での判定も難しく、術中迅速病理組織診にて悪性と診断され過大手術を施行された症例の報告もあります。このため、画像上、乳癌が疑われるが、細胞診や生検でも確定がえられず、乳管腺腫も否定できない場合、術中病理診断の良悪性の判定による手術術式の選択はなるべく避け、切除生検の永久標本で診断してから、あらためて方針を決定する方が安心であると考えられます。
正常乳腺細胞から癌化していく第1段階では、正常細胞の過剰な増殖を引き起こし、この状態を乳管過形成(usual ductal hyperplasia, UDH)と呼びます。そして、2段階目の過程で、過形成の細胞が変異をはじめ、正常でない異型細胞(atypical cells)に変化します。この変化の段階を異型乳管過形成(atypical ductal hyperplasia, ADH)と呼びます。「その形態が非浸潤癌に非常に似ており、非浸潤癌の病理診断基準の一部を満たすが、これを完全に満足していないもの」を異型過形成と定義しています。この場合も異型乳管過形成(atypical ductal hyperplasia: ADH)と異型小葉過形成(atypical lobular hyperplasia: ALH)の2種類があります。
両者とも、現在、病理学的には乳腺症の一部として取り扱われ、将来悪性化の可能性が高いものとされています。つまり、これら2つの疾患は、前癌病変または悪性と良性の境界病変と考えられていますが、実際にはきわめて微小な癌である可能性もあります。診断基準に大きさが含まれていますが、これらの病変に対する考え方や取り扱いは病理診断医や研究者により異なっており、臨床医としては、患者さんに単純に「組織診断が癌ではなかった」と説明する訳にはいかない点が悩むところです。
一般に、良性であれ、悪性であれ、病変部組織をcore-needle biopsy(CNB:太針生検)や吸引組織生検(マンモトーム生検、バコラ生検)により部分的に採取して、病理診断されます。しかし、これらの方法によりADHやALHと診断されたケースで、改めて切除生検を行なうと、4-10%が非浸潤癌または浸潤癌と診断されたと報告されています。したがって、これらの検査法は組織の一部を採取する検査のため診断には限界があり、確定診断のためには腫瘍の切除生検が必要です。
また、異型過形成と診断された女性の約10-30%が、10-25年の間に浸潤性乳管癌を発症するとの報告もあり、厳重な経過観察が必要です。このため、異型過形成を微小癌として扱っている専門医もいます。
乳腺症は、中年期〜更年期の女性にみられる乳房のしこりや痛みなど、乳癌によく似た症状が表れる病気です。
乳房は、20代~30代の女性では、妊娠、授乳に備えて、そのほとんどが乳腺組織で占められています。ところが、授乳の必要がなくなった中年以後の女性では、乳腺組織が脂肪組織に少しずつ置き換わっていきます。
30代後半から40代の女性の乳房はその間の過渡期で、乳腺組織と脂肪組織が交じった状態にあります一般に、乳腺は年齢とともに次第に硬くなりますが、中年〜更年期以後では脂肪組織の中に残った乳腺が“しこり”として感じることがよくあります。また、若い女性でも、女性ホルモンのバランスがくずれた場合に、乳腺が腫れ、痛みが出たりすることがあります。乳腺症は、このようないろいろな病態をひとまとめにしたもので、病理学的にはいくつかの種類に分類されています。欧米ではこの乳腺症という概念はなく、fibrocystic disease(線維嚢胞性疾患)と呼ばれています。
こうした変化は、女性の正常な生理的な体の変化であり、通常は治療の必要はありません。ただ、日常生活に支障があるようなひどい痛みが5~6カ月以上続くような乳腺症では治療が必要となることもあります。治療法は、女性ホルモンの働きを抑える薬を使用したり、女性ホルモンそのものを投与する場合もあります。その上に鎮痛薬などを2~3カ月使います。これらの薬物療法は根本的な治療法ではありません。また、副作用として太ったり、肝臓に障害を起こしたり、血栓ができやすくなったりします。漢方薬が有効な場合もあります。これらホルモンに影響する薬物は乳癌発癌への影響が否定できないため、当院では原則として行いません。
乳腺症の中には、まれに癌に移行しやすいタイプ(乳管乳頭症、異型乳管過形成、異型小葉形成、閉塞性腺症、硬化性腺症など)もあり、また、乳癌との鑑別が困難な場合もあります。当院では、中年期以降で乳房のしこりや痛みを訴える場合、乳癌の可能性も考慮し、触診、マンモグラフィー(乳房のレントゲン撮影)、超音波などで検査をします。確実な診断が難しい場合には、針で細胞を吸引して、顕微鏡で調べ、癌でないことを確かめます(穿刺細胞診、吸引組織生検)。診断が難しい場合には、しこりの一部または全てを切り取って顕微鏡で調べる切除生検が必要なこともあります。
以上のように乳腺症とはいろいろな病態をひとまとめにした概念です。またタイプによっては癌に移行しやすいものもありますので、当院では6ヶ月~1年毎の定期検査をすすめています。
嚢胞は、乳汁の流れる乳管の一部が狭くなったり閉塞したために、分泌物が貯留してできた袋のようなものです。基本的には中年期〜更年期の女性にみられる乳腺症の一部に分類されますが、若い女性でもみられることがあります。ホルモン環境の変化や乳腺炎のような炎症によって乳管の状態が変化してできるものですから、経過観察中に大きさが変化したり、小さなものでは消失することもあります。
嚢胞の症状は、硬い腫瘤として触れることが多いのですが、検診などで偶然見つかるような嚢胞では触診で触れないこともよくあります。また、1つだけではなく、数個から無数にある場合までいろいろで、両側の乳房にあることもしばしばです。 袋の中に液体がたまること自体は問題ないのですが、大きくなると疼痛が出ることもあります。その場合は、注射針で穿刺して内容を抜き取りますが、幾度か穿刺を繰り返しているうちに貯まらなくなることもあります。
嚢胞で一番気をつけなければならないことは、嚢胞内腫瘍の発生です。多くは乳頭腫(嚢胞内乳頭腫)という良性のものですが、まれに悪性の乳頭癌や乳頭腺癌(嚢胞内乳頭癌)ができたりします。このため、嚢胞がある場合は定期的に検査を行なって、嚢胞内に腫瘍が発生していないかを調べることが大切です。もし、嚢胞内に腫瘍のようなものが見つかった場合には、注射針で穿刺をして、内容液とともに細胞を吸引して顕微鏡で癌細胞が混ざっていないかを調べます(穿刺細胞診)。 嚢胞内腫瘍が見つかった場合、細胞診を行ない、癌細胞が見られなければ定期的に検査をしながら経過を観察します。しかし、細胞診で癌細胞が検出されなくても、腫瘍が増大したり、形が変化してきた場合は、癌を疑って切除し、顕微鏡で調べる切除生検を行なう必要があります。中高年の女性の嚢胞内腫瘍は、細胞診で癌細胞が検出されなくても、切除生検をする方が安心かもしれません。
以上のように、嚢胞の場合は、嚢胞内に腫瘍があるかどうかによって、対応が異なります。当院では、普通の嚢胞の場合は6ヶ月~1年毎の、嚢胞内に腫瘍が見られる場合には、3か月毎の定期検査を行なうようにしています。





















